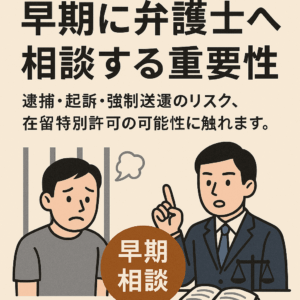このページの目次
事例紹介:永住者Aさんのフェンタニル使用事件
永住資格を持つ外国人のAさんは、母国からごく少量のフェンタニルを日本に持ち込み、国内で自己使用しました。しかし病院に搬送され、診察で麻薬使用の疑いが浮上しました。尿検査などの結果、Aさんがフェンタニルを使用していたことが判明し、その場で逮捕されてしまいました。Aさんには前科がなく、今回が初めての違法行為でした。このケースを通じて、逮捕・起訴から在留資格への影響までを見ながら、「早期に弁護士へ相談する重要性」を考えていきます。
フェンタニル使用の刑事罰:初犯でも油断できない
フェンタニルとは医療用鎮痛剤として使われる成分ですが、乱用すると幻覚症状を引き起こし、過剰摂取により死亡事故も起きている非常に危険な薬物です。そのため日本では「麻薬及び向精神薬取締法」(麻向法)により輸入・所持・使用が厳しく禁止されています。フェンタニルは同法の規制対象(別表第一77号が指定する麻薬)に指定されており、正当な医療目的以外で使用しただけでも犯罪となります。
この麻向法66条の2第1項では、麻薬(フェンタニル等)の使用罪の法定刑は「7年以下の拘禁刑」と定められています。つまりAさんの場合、たとえ少量の使用でも最悪7年の拘禁刑(懲役刑)を科される可能性が法律上はあるわけです。ただし実際の量刑は個々の事情で異なり、一般に初犯で自己使用目的のみであれば比較的軽い傾向があります。過去の判例や傾向からすると、前科のない初犯の薬物使用者には執行猶予付きの判決が下されるケースもあります。Aさんも使用量がごく少量・使用回数も1回のみ・前科なしという状況から、執行猶予付きの懲役刑(いわゆる執行猶予判決)になる可能性が高いと予想されます。
しかし油断は禁物です。量刑は以下のような要素で重くも軽くもなります:
- 薬物の量: 持ち込んだ・使用した量が多いほど刑は重くなります。少量とはいえ油断できません。
- 使用(犯行)の回数: 常習性が疑われると厳罰化しやすく、回数が増えるほど悪質と見られます。
- 前科の有無: 前科があると再犯とみなされ刑が重くなります。初犯は情状酌量の余地があります。
Aさんは幸い初犯でしたが、もし営利目的(売買目的)で麻薬を扱っていた場合、初犯でも実刑(執行猶予なしの懲役刑)となる可能性が高くなります。このようにケースによって結果が大きく変わるため、刑事手続きの早い段階から専門家である弁護士と十分に打ち合わせをして対応策を練ることが極めて重要です。
逮捕から起訴まで:外国人だからこそのリスク
逮捕された後、警察による取り調べや身柄の拘束(勾留)が行われます。薬物事案では証拠隠滅や逃亡の恐れから逮捕・勾留が長引く傾向があり、場合によっては共犯者捜査のために接見禁止(家族などとの面会禁止)が付くこともあります。接見禁止が付されると弁護士だけが面会可能となるため、家族であっても本人と直接会えません。このような状況下でも弁護士であれば接見して本人の状況を確認し助言できます。早めに弁護士に依頼しておけば、孤立しがちな被疑者(本人)を励ますこともできます。
検察官が起訴(正式な裁判にかけること)するかどうかの判断は、事実関係を認めているか否か,証拠の強さによって決まります。Aさんの場合、尿検査で陽性反応が出ている以上起訴され公判にかけられる可能性が高いでしょう。
また,起訴後は保釈が認められない限り裁判が終わるまで勾留が続きます。保釈を勝ち取るには裁判所への請求と保証金の納付が必要で、法律の専門知識が要求されます。ここでも弁護士のサポートが不可欠です。早期に弁護士に相談していれば、勾留に対する不服申立てや保釈請求など迅速な対応が可能となり、場合によっては本人を早く解放させて通常の生活に近い状態で裁判に臨ませることも期待できます。
有罪判決で待ち受ける在留資格への影響:強制送還のリスク
Aさんのような外国人が日本で罪を犯し有罪判決を受けると、刑事罰だけでなく在留資格への重大な影響があります。日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)24条4号チという規定では、麻薬及び向精神薬取締法などの薬物に関する法律に違反して有罪判決を受けた外国人は退去強制(強制送還)の対象になると定められています。これは執行猶予付き判決であっても例外ではありません。執行猶予が付いて刑務所に行かずに済むとしても、「有罪判決を受けた」という事実に変わりはないため、入管法上は退去強制事由(国外退去させる理由)に該当してしまうのです。
その結果、原則として日本からの強制退去が待ち受けます。永住者であっても、この退去強制を回避しない限り日本に住み続けることはできません。Aさんも仮に執行猶予判決となった場合でも、この規定に該当するため強制送還のリスクが生じます。
在留特別許可という最後の望み
とはいえ、一度の過ちで即座に生活基盤を奪われてしまうのは本人・家族にとって大変深刻です。そこで法律上、退去強制の対象になった外国人にもわずかながら救済の途があります。それが「在留特別許可」と呼ばれる制度です(出入国在留管理局HP)。退去強制となる事情があっても、法務大臣の裁量で特別に日本への在留を許可してもらえる可能性があります。例えば日本人の配偶者や子どもがいる場合、長年日本で暮らして地域に溶け込んでいる場合などは、積極的に考慮される「在留すべき事情」となり得ます。
Aさんの場合、永住者ということは日本に生活の本拠があり、家族や仕事など日本での生活基盤があると考えられます。それらを根拠に「日本に引き続き在留する必要性(情状)」を主張できれば、在留特別許可が与えられる余地があります。ただし在留特別許可は自動的にもらえるものではなく、あくまで「特別に許可」されるものです。申請や審理の過程で日本に残るべき正当な理由を具体的に示し、入管当局に認めてもらわなければなりません。
弁護士ができること:刑事弁護から在留特別許可のサポートまで
弁護人(弁護士)としてAさんのようなケースでできることは大きく分けて2つあります。一つは刑事手続における弁護活動、もう一つは在留資格に関わる手続(在留特別許可)の支援です。
- 刑事弁護活動: まず刑事裁判においてできる限り情状酌量を引き出し、量刑を軽減するよう努めます。具体的には、犯行に至った経緯や本人の反省状況、今後再犯しないための環境(治療計画や家族の監督体制など)を丁寧に主張し、執行猶予付き判決や減刑を目指します。初犯であることや使用量の少なさなど有利な事情は最大限強調し、裁判官に「更生可能性が高い」と判断してもらうことが重要です。また、勾留中であれば早期の保釈請求も行い、社会復帰しやすい環境で裁判を受けられるよう手配します。
- 在留特別許可のためのサポート: 有罪判決によって退去強制手続きに移行した場合、在留特別許可の申請手続きを全力でサポートします。具体的には、本人および家族の状況を詳しくヒアリングし、日本に残る必要性を示す資料(家族関係を証明する書類、嘆願書、雇用証明、納税記録など)を収集・提出します。
なぜ早期相談が重要なのか:逮捕後すぐ動くことのメリット
以上のように、外国人が罪を犯した場合には「刑事罰」と「在留資格の剥奪」という二重のリスクに直面します。しかし逆にいえば、早めに専門の弁護士に相談することで刑事手続と入管手続の両面に備えることが可能となります。逮捕直後から弁護士が付けば、取り調べ段階での助言や権利擁護(黙秘権の行使や供述調書のチェックなど)を受けられ、不利な証言を避けられるかもしれません。また、家族との連絡調整や必要書類の収集も早期から開始できます。裁判で有利な証拠や嘆願書の準備、さらには在留特別許可のための資料作成も、時間的猶予をもって進められます。
一方、対応が遅れると手遅れになるリスクがあります。例えば有罪判決が確定してから慌てて在留特別許可の準備を始めても、充分な主張を組み立てる時間がないかもしれません。場合によっては拘束中に強制送還の日程が進んでしまい、準備が整わないまま本国送還となりかねません。早期に信頼できる弁護士に相談し、刑事弁護と入管対応を一貫して依頼しておけば、そのような最悪の事態を避けられる可能性が高まります。
おわりに:家族のためにも迅速な相談を
永住外国人やそのご家族にとって、日本で築いた生活基盤を犯罪によって失うことは想像を絶する不安でしょう。しかし、逮捕・起訴されたとしても諦めず、まずは弁護士に相談することが肝心です。専門の弁護士であれば、刑事裁判での戦略立案から在留特別許可の申請まで総合的にサポートしてくれます。Aさんのケースでも述べたように、初犯なら執行猶予の可能性があり刑務所行きを避けられるかもしれません。さらに判決後も適切に対応すれば、在留特別許可を得て日本に住み続ける道が開ける可能性もあります。そのためには時間との勝負です。問題が発覚した時点で一刻も早く弁護士に相談し、今後の見通しや取るべき手段についてアドバイスを受けてください。逮捕・起訴・強制送還という最悪の結果を防ぎ、かけがえのない生活と家族を守るために、早期の弁護士相談が何より重要なのです。