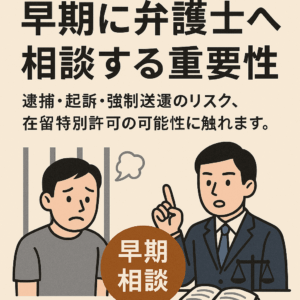Author Archive
『京都新聞DIGITAL』にコメントが掲載されました
『京都新聞DIGITAL』にコメントが掲載されました

永住者が私文書偽造罪・詐欺罪で逮捕された場合の刑事弁護の必要性と強制送還リスク
日本で長年生活し永住権を持つ外国人であっても、罪を犯して有罪判決を受ければ、日本での在留に大きな影響が及ぶ可能性があります。
実際に、永住者の方が私文書偽造罪や詐欺罪で検挙されるケースも起きています。
こうした場合、刑事上の処罰だけでなく、強制送還(退去強制)という重大なリスクも考慮しなければなりません。
この記事では、私文書偽造罪・詐欺罪で検挙された永住者のケースをもとに、刑事事件が永住者に与える影響や強制送還の可能性、永住資格取消の条件、家族(配偶者・子)への影響、そして早めに弁護士を依頼するメリットや、刑事弁護と入管手続きの両面に対応できる専門家の重要性について具体的に解説します。最後に、詐欺事件の弁護経験や外国人支援の実績が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のサポート内容も紹介します。
1. 私文書偽造罪と詐欺罪が永住者に与える刑事的・入管的影響
私文書偽造罪や詐欺罪は非常に重大な犯罪であり、永住者であっても例外ではありません。
詐欺罪(刑法246条)の法定刑は10年以下の拘禁刑と重く、私文書偽造罪(刑法159条)の法定刑も3月以上5年以下の拘禁刑とされています。
実際の詐欺事件では、犯行の過程で書類を偽造する場合も多く、文書偽造罪と詐欺罪が併せて適用されるケースも少なくありません。有罪判決となれば刑務所に服役する可能性があるのはもちろん、その刑の重さによっては在留資格にも影響が及びます。特に1年を超える実刑判決が下された場合、永住者であっても入管法に基づき強制送還となります。逆に、執行猶予付き判決や1年以下の刑であれば直ちに退去強制とはならない可能性もあります。いずれにせよ、刑事裁判の結果は永住資格に直結し得る重大事であり、十分な注意と対策が必要です。
2. 強制送還の可能性と入管法の規定
外国人が日本で刑事事件を起こし有罪判決を受けた場合、その内容によって入管法に定める退去強制事由(強制送還の理由)に該当することがあります。
一般的には「1年以上の拘禁刑」が退去強制の対象とされており、永住者であっても例外ではありません。つまり、たとえ永住資格を持っていても1年を超える実刑判決を受ければ、刑期終了後に原則として強制送還が可能となります。一方、刑期が1年以下の場合や執行猶予付き判決の場合は、特別な事情がない限り直ちに強制送還とはなりません(もっとも、麻薬など特定の犯罪では、判決の種類にかかわらず有罪になった段階で強制送還の対象となります)。強制送還のリスクがある以上、刑事手続だけでなく入管上の対応策も常に念頭に置いておく必要があります。
3. 永住資格が取り消される条件
永住者の在留資格(いわゆる永住権)は一度許可されれば期限のない強固な資格ですが、一定の場合には取り消されることがあります。主な取消事由として、次のようなケースが挙げられます。
• 不正手段による永住許可取得:偽造書類の提出や虚偽の申告などにより不正に永住許可を得ていたことが発覚した場合、永住許可は取り消されます。
• 重大な犯罪行為:重大な犯罪をした場合、永住資格も結果的に剥奪され退去強制となります。現行法でも1年以上の実刑判決だけでなく、文書偽造罪や麻薬犯罪等の有罪判決があれば永住資格は失われます。加えて、2024年の改正により詐欺罪など一定の重大犯罪で有罪となれば取消可能になりました。
• 納税・社会保険料の故意の未納:2027年に施行される入管法の改正により、悪質な税金等の滞納も永住許可の取消事由となります。
このように、永住資格といえども違法・不適切な行為があれば取消される可能性があります。特に刑事事件による有罪判決は深刻な影響を及ぼしうるため、永住者の方は十分注意が必要です。
つまり、文書偽造や詐欺の検挙されたケースの場合、有罪となれば、実刑判決を受けなくとも永住許可が取り消され、日本から退去強制となる可能性が大きいのです。
4. 家族への影響(配偶者・子の在留資格や生活)
永住者本人が刑事事件で逮捕・起訴されると、その配偶者や子を含む家族にも多大な影響が及びます。まず生活面では、家計の中心者が拘束・服役すれば収入が途絶え、家族の精神的負担も大きくなるでしょう。さらに法的な面でも、家族の在留資格に変化が生じる可能性があります。
例えば、配偶者が「永住者の配偶者等」の在留資格で滞在している場合、主たる永住者が強制退去となればその配偶者ビザの更新はできず、永住者とともに帰国するか、「定住者」など別の在留資格への変更が必要になってきます。また、子どもが外国籍で永住者の子として在留している場合、親の永住資格が取消されても直ちに子の資格が失われるわけではありませんが、将来の在留資格更新時には扶養者である親が日本にいなくなるため、資格の変更や帰国を検討せざるを得なくなる可能性があります。
このように、永住者本人の刑事事件は家族の生活基盤や在留資格にも影響を及ぼします。日本に残る家族が離れ離れになってしまう事態を防ぐためにも、早い段階から法的な対策を講じることが重要です。
5. 弁護士の早期介入によるメリット
永住者が刑事事件で検挙された場合、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することが極めて重要です。早期に弁護士が介入することで、次のようなメリットが期待できます。
• 迅速な対応と身柄解放:弁護士が早期に動けば保釈により身柄を早期に解放できる可能性があります。また、取調べに関する助言を受けることで不利な供述を避けられます。
• 被害者との示談交渉:被害者と示談を成立させることで、不起訴や執行猶予となる可能性が高まります。もっとも、本人が被害者と直接交渉するのは困難なため、弁護士が代理で交渉します。
• 入管手続への備え:刑事手続と並行して退去強制への対策も講じることができます。家族の嘆願書などを早めに整え、在留特別許可の申請に備えることが可能です。
このように、弁護士を早期に依頼することで刑事手続と入管手続の双方に万全の備えをすることができます。特に永住者の刑事事件では、今後も日本に住み続けたいという本人・家族の願いを守るためにも、初動の対応が肝心です。
6. 刑事弁護と入管手続きの両面に対応できる専門家の重要性
前述のとおり、外国人の刑事事件では刑事裁判の行方が在留資格に密接に関わってきます。そのため、刑事手続と入管手続の両方に精通した専門家に依頼することが理想的です。刑事事件のみを扱う弁護士では判決後の入管対応が後手に回るおそれがあり、逆に入管業務のみの専門家では刑事裁判自体の弁護活動ができません。両方の知識を備えた弁護士であれば、判決確定前の段階から退去強制への対策まで一貫して対応できます。永住者の方が自身や家族の日本での生活を守るためには、このような総合力を持つ専門家のサポートが不可欠と言えるでしょう。
7. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
永住者が関わる文書偽造・詐欺事件の弁護を依頼するなら、刑事事件と入管法務を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が心強い味方になります。
同事務所は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、文書偽造罪や詐欺罪をはじめとする財産事件で多数の実績があります。示談交渉や迅速な対応によって不起訴処分や執行猶予判決を獲得したケースも多く、依頼者への丁寧な説明も高く評価されています。また、外国人の刑事弁護にも注力しており、入管対応についても経験豊富な弁護士が在籍しています。必要に応じて質の高い通訳を迅速に手配でき、文化や言語の違いにも配慮した弁護が可能です。無料法律相談も土日夜間含め24時間体制で受け付けているので、永住者の方やご家族が文書偽造や詐欺事件でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
永住者が売春あっせんで逮捕されたら?刑事処分と退去強制リスクを徹底解説
風俗店やマッサージ店を装い売春行為を行っていた場合、たとえ永住者であっても刑事罰や在留資格への重大な影響が及ぶ可能性があります。本記事では、売春防止法が規定する売春あっせんの刑事責任と処罰内容、永住者に対する退去強制・在留資格取消しの基準、弁護士が提供できる刑事弁護および入管対応策、そして実際に同様の案件を扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の実績について解説します。法律的根拠と実務的ポイントを押さえ、適切な対応策を検討する一助としていただければ幸いです。
売春あっせんとは何か―適用法令と犯罪成立要件
「売春あっせん」とは、売春をしようとする人と客を仲介・紹介する行為を指し、売春防止法により明確に禁止された犯罪行為です。売春そのものは同法で禁止されているものの処罰規定はなく、当事者同士が合意した性交自体は刑事罰の対象外です(ただし、自分自身で客を、いわゆる立ちんぼやインターネット上を介して売春の相手を見つけた場合には、処罰対象となり得ます。)。しかし、第三者が売春を勧めたり周旋(仲介)した場合は処罰対象となり、たとえ店舗型のマッサージ店やガールズバーを装っていても、実質的に顧客と女性を引き合わせて性的サービスを提供していれば「売春周旋罪」が成立します。例えば「客引きして性行為相手を紹介する」「デリバリーヘルスの名目で実際は本番行為をさせている」等は、この売春あっせん行為に該当し得ます。
売春防止法が定める処罰内容と刑罰の重さ
売春あっせん(売春周旋罪)に対する法定刑は2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金と規定されています(売春防止法6条)。一見すると刑の上限は高くないようにも思えますが、拘禁刑が含まれているため有罪になれば前科が付きうる重大な犯罪です。実際の量刑は事案の悪質性により大きく異なります。単独でこっそり行っていた程度の比較的軽微なケースであれば、起訴されても罰金刑や執行猶予付き判決にとどまる可能性が高く、初犯で深く反省している場合には不起訴処分で終結するケースもあります。一方、組織的・常習的に大規模な売春クラブを運営し暴力団の資金源になっているような悪質事案や、児童を対象とした売春あっせんが絡む場合などは実刑判決(拘禁刑)となる可能性が高まります。つまり、売春あっせん罪の法定刑自体は比較的軽い部類ですが、その科される刑罰の重さは事案の態様次第で大きく変わり得る点に注意が必要です。
永住者でも退去強制となり得る事例と法律上の基準
日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)では、たとえ「永住者」の在留資格を有する外国人であっても、一定の重大な違反行為を行えば在留資格の取消しや強制退去(強制送還)の対象になり得ます。その典型例の一つが売春に関わる行為です。入管法第24条は、外国人が「売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務」に従事した場合を退去強制事由の一つとして明記しています。つまり、売春防止法に違反する行為で有罪判決を受ければ、永住者であろうと在留資格を剥奪され強制送還される可能性が生じます。実務上も、入管当局は売春事犯に厳しく対応しており、売春事件で起訴された被告人の判決公判には入管職員が傍聴に訪れ、有罪判決が言い渡されると同時に被告人を収容して退去強制手続に移行する運用が現に行われています。このように、永住資格があっても絶対安心ではなく、売春あっせん等の犯罪によっては直ちに日本からの退去を余儀なくされるリスクがあるのです。
売春絡みで在留資格を失う具体的ケースと退去強制の実例
入管法の規定する退去強制事由は抽象的に感じられるかもしれませんが、実際に売春に関与したことで在留資格を失ったケースも報告されています。
例えば2020年11月、東京・日暮里の中国エステ店(いわゆる「チャイエス」)が無許可営業の摘発を受け、40代の日本人経営者と30代の中国人女性店長が風営法違反容疑で逮捕されました。その際、その店で働いていたベトナム人女性従業員3名も売春への関与や不法就労の疑いで身柄を拘束されています。この店には約30人もの外国人女性が在籍し、月に1億円近い売上を上げていたと報じられましたが、逮捕後、外国人従業員らは入管法違反で処罰され、順次強制送還の手続きに移行したものと推測されます。
表向き「マッサージ店」「ガールズバー」と称していても実態が売春であれば風営法上の風俗営業に該当し、在留資格に致命的な影響が及んでしまいます。入管法24条に該当する行為があった時点で永住者であっても退去強制の対象となり(実際、麻薬・覚醒剤取引や売春斡旋などで拘禁刑(執行猶予判決の場合をも含みます。)を科されれば退去強制手続きが開始されてしまい)、以降の在留は原則認められなくなります。
もっとも、家族関係など特段の事情がある場合には在留特別許可により日本に留まれる例もあり、例えば日本人配偶者を持つ永住者が退去強制事由に該当したものの特別に残留が許可されたケースでは、一旦永住資格は失うものの在留特別許可により退去を免れ、数年後に再度永住許可を申請できたという報告もあります。しかしこれは極めて例外的な措置であり、大前提として売春に関与すれば永住資格すら剥奪されるという厳しい現実を認識しておかなければなりません。
刑事手続において弁護士ができること(刑事弁護)
こうした売春あっせん事件で逮捕・起訴された場合、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼することが極めて重要です。弁護士は逮捕直後から取調べへの同席や適切な助言を通じて被疑者の権利を守り、不当な自白の強要などを防ぎます。また、検察官との交渉においては、違法行為に至った経緯や本人の反省、更生の意思などの有利な情状を主張し、起訴猶予(不起訴)や罰金刑で済ませるよう働きかけることが期待できます。
実際、前述のように売春防止法違反は初犯で反省が顕著な場合、不起訴処分や略式罰金で済むケースもあります。弁護士の適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を得られれば実刑を免れますし、罰金刑で済めば長期間の身柄拘束や収監を避けることができます。これは本人の社会復帰に資するだけでなく、後述する入管手続き上も極めて重要です。なぜなら、刑が軽いほど退去強制を回避できる余地が広がる可能性があるためです。さらに外国人被告の場合、日本の裁判では言葉の壁も問題になりますが、弁護士が通訳人と連携して法廷で不利益が生じないよう配慮することもできます。このように、刑事弁護人の果たす役割は逮捕後から判決に至るまで非常に大きいと言えるでしょう。
入管対応において弁護士ができること(在留手続と特別許可)
刑事処分が下った後は、入国在留管理庁による退去強制手続きが問題となります。ここでも弁護士が果たす役割は重要です。刑事事件を担当した弁護士であれば、判決前から入管対応を見据えた活動を並行して行います。具体的には、在留資格取消しや退去強制を避けるため、情状に配慮した在留特別許可を求める申出の準備を進めます。例えば、日本に日本人の配偶者や未成年の子どもがいる、長年日本で生活基盤を築いて納税義務も果たしている、といった事情は強力な在留の理由となり得るため、そうした人道的配慮事項を綿密に立証して入管当局に訴えていきます。
また、弁護士は必要に応じて入管当局と交渉し、在留特別許可(法務大臣の裁量で退去を猶予し在留を認める制度)の取得を目指します。入管手続は行政処分の領域ですが、弁護士であれば聴聞の場で本人の代理人となって意見を述べたり、取消し処分に対する不服申立てを行うことも可能です。
実務上、刑が確定すると即日収容・送還となる例もありますが、弁護士が事前に入管側と連絡を取り、自主的な出頭や旅券手配などを調整することで「判決直後の即時収容」を避けたケースもあります。いずれにせよ、「日本に残りたい」という意思がある場合は刑事手続の段階から入管対策を講じておく必要があるため、刑事弁護と入管対応を一貫して依頼できる弁護士に早めに相談することが肝要です。
類似案件における弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の実績
今回のケースのように、売春防止法違反と入管法上の問題が絡む事件を扱うには、刑事弁護と外国人の在留手続き双方に精通した法律事務所のサポートが不可欠です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っており、風営法違反や入管法違反を含む様々な刑事事件で豊富な実績を有しています。同事務所には外国人案件に精通した弁護士が在籍しており、言語の壁がある場合でも適切に対処できる体制が整っています。実際、当事務所が運営する入管問題専門サイトでは、外国人従業員を雇って無許可営業をしていた風俗店の摘発事例(前述の日暮里のケースに類似するケース)について解説を行うなど、蓄積された知見を積極的に発信しています。これらの情報提供は、同事務所が風俗店経営に絡む刑事事件と外国人の在留問題を数多く手掛けてきた裏付けと言えるでしょう。また、初回無料相談を実施し、逮捕前後を問わず365日24時間相談に応じる体制を整えるなど、依頼者が一刻も早く適切な助言と弁護を受けられるよう尽力しています。永住者の方が売春あっせん容疑でお困りの場合、同事務所のように刑事弁護と入管対応の両面に強い弁護士に相談することで、最善の結果を目指すことができるでしょう。
まとめ
風俗営業を装った売春行為のあっせんは、売春防止法違反として拘禁刑も含む刑事罰の対象となり、永住者であっても有罪となれば在留資格の取消し・強制送還が現実味を帯びる深刻な事態です。 しかし、早期に専門の弁護士のサポートを受けることで、刑事手続上は不起訴や執行猶予を獲得し、入管手続上も在留特別許可の可能性を模索する道が開けます。 万一このような嫌疑をかけられた場合には、本記事で解説したポイントを踏まえ、速やかに信頼できる弁護士に相談することを強くお勧めします。専門的な知識と経験に基づく適切な対応によって、人生を左右する危機を乗り越える可能性を最大限に高めましょう。
外国人が傷害事件で逮捕?刑事処分と強制送還リスク・弁護士ができる対応とは
事例紹介:介護現場で起きた傷害事件
介護施設で働く外国人技能実習生Aさんは、日々利用者の介護業務に従事していました。ある日、ベッド上で介護中の利用者が突然暴れ出し、Aさんは驚いて利用者の顔を平手打ちしてしまいました。その結果、利用者は口の中を切る軽傷(全治1週間程度の出血を伴う怪我)を負い、同僚の目撃もあって数日後にAさんは傷害の容疑で逮捕されてしまいます。このようなケースでは、どのような刑事処分を受ける可能性があるのでしょうか? そして、技能実習生であるAさんは強制送還(退去強制)の対象となってしまうのでしょうか? 以下で詳しく解説していきます。
傷害罪で問われる可能性のある刑事処分
まずAさんが疑われている傷害罪(刑法204条)についてです。法律上、「傷害」とは人の生理機能に障害を与えることであり、出血を伴う怪我を負わせた場合などはこれに該当します。傷害罪が成立すると15年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑罰が科され得ます。実際にどのような刑事処分となるかは様々な事情を考慮して判断されます。
傷害事件の量刑(処分の重さ)は、以下のようなポイントによって決まります。
-
怪我の程度:被害者の負った怪我が重ければ重いほど、科される刑も重くなります。
-
被害者との関係性:加害者が被害者を保護すべき立場(例えば介護職員と利用者)の場合、犯行は悪質と判断され厳しく見られます。
-
前科の有無:前科・前歴があると不利な事情となり、刑が重くなる傾向があります。
-
被害弁償:被害者への謝罪や示談による賠償が行われていれば、情状酌量され刑事処分が軽減される可能性があります。
今回のAさんの事例に照らすと、怪我の程度は比較的軽微であり、Aさん自身も前科はありません。しかし一方で、本来利用者を守るべき介護職員が利用者に怪我を負わせた点は重く受け止められます。
総合的に考えると、罰金刑では済まず執行猶予付きの懲役刑(拘禁刑)が言い渡される可能性が高いと言えるでしょう。つまり、裁判で有罪判決が下りるものの一定の期間刑務所に行くことは猶予される(執行猶予が付く)ケースが予想されます。
有罪判決による強制送還のリスク
Aさんのような技能実習生が傷害罪で有罪判決を受けると、たとえ執行猶予付きでも母国への強制送還につながるリスクがあります。日本で築いた生活やキャリアが突然断たれてしまう可能性もあるのです。
次に、在留資格への影響(退去強制=強制送還のリスク)について説明します。日本の入国管理法では、一定の犯罪で有罪となり懲役刑・禁錮刑(執行猶予付きも含む)を言い渡された外国人は、その在留資格によっては退去強制(強制送還)の対象になります。特に技能実習生を含む「別表第一」に分類される就労系の在留資格で日本にいる外国人が傷害罪などの罪で有罪判決を受けた場合、執行猶予付きであっても退去強制事由に該当してしまうのです。これは入管法24条4号の2に定められた規定で、傷害罪がその対象犯罪に含まれているためです。
以上の法律の仕組みから、今回のAさんのケースでは執行猶予付きの懲役刑になれば在留資格の取消し・収容を経て強制送還となる可能性が高いです。せっかく日本で働いてきたAさんは、有罪判決が確定すると日本にとどまれなくなり、家族や職場とも離ればなれになってしまう恐れがあります。強制送還となれば、再入国も長期間禁止されることが一般的です。このように刑事処分だけでなく、その後の強制送還という重大な結果が待ち受けている点で、外国人にとって日本で事件を起こすことは日本人以上に大きなリスクを伴います。
刑事処分・強制送還を避けるために専門家に相談を
このように、技能実習生のAさんには懲役刑(執行猶予付き)による前科と強制送還という二重の危機が迫っています。しかし、適切な対応を取ることで刑事処分を軽減し、退去強制処分を回避できる可能性があります。そのためには一刻も早く弁護士などの専門家に相談・依頼することが極めて重要です。
弁護人(弁護士)として考えられる対策・サポートには、主に次のようなものがあります。
-
被害者との示談交渉:早期に被害者と示談を成立させることで、不起訴処分(起訴されない)や罰金刑にとどめてもらえる可能性があります。不起訴や罰金刑であれば有罪判決による懲役刑を避けられるため、退去強制の事由に該当しなくなり、日本に残れる可能性が大いに高まります。特に起訴前に示談がまとまれば検察官が起訴猶予とするケースもあり得るため、時間との勝負です。専門家である弁護士は示談交渉の進め方や必要な謝罪・補償の方法について的確なアドバイスと交渉代行を行ってくれます。
-
退去強制処分への対抗策準備:万一有罪判決(執行猶予付き懲役刑)が避けられず退去強制事由に該当してしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。弁護士は入管当局の手続において在留特別許可が認められるよう、退去強制処分をすべきでない事情を収集・主張することができます。例えば、日本での雇用実績や社会貢献、本人の反省状況、被害者から許されていること、さらには日本に生活基盤や家族がある場合の情状などを丁寧に示すことで、例外的に在留が許可されるよう働きかけます。また、入国者収容所での仮放免手続や異議申立てなど、退去強制のプロセスにおける対応についても専門的なサポートを受けることができます。
これらの対応は専門的な知識と経験が不可欠であり、自分一人や周囲だけでは適切な判断・交渉を行うのは難しいでしょう。だからこそ、Aさんのような状況に置かれた場合には、できるだけ早く刑事事件・入管案件に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。早期に専門家へ依頼することで、将来の日本での生活とキャリアを守れる可能性が大きく高まります。
雇用主や家族ができるサポートも重要
技能実習生など外国人の方が事件に巻き込まれた際には、本人だけでなく雇用主や家族の協力・サポートも非常に重要です。雇用主やご家族ができる具体的な支援として、次のようなものが挙げられます。
-
早期の専門家相談を後押しする: 本人が逮捕・勾留されて動けない場合、雇用先の上司や家族が率先して弁護士を探し依頼することが大切です。雇用主にとっても貴重な技能実習生が強制送還されてしまえば人手を失うことになり、事業にも支障が出ます。家族にとっても大切な家族が国外退去となれば生活設計が狂ってしまいます。周囲の迅速な働きかけで、弁護活動のスタートを1日でも早めることができます。
-
情状証人・嘆願書の協力: 雇用主は「引き続き雇用したい」「更生を手助けする」といった内容の嘆願書を作成したり、裁判で情状証人として出廷して被告人(本人)の人柄や今後の監督を約束する証言をしたりすることが考えられます。家族も同様に、本人が反省し更生できるよう支える意思を示す嘆願書を提出することで裁判官の心証に良い影響を与えられるでしょう。
このように、周囲の支援体制が整っていること自体も「日本で更生できる環境がある」ことのアピールとなり、在留特別許可を求める上でも有利に働く場合があります。雇用主や家族は単なる傍観者にならず、積極的に専門家と連携して支えていくことが重要です。
まとめ:迅速な専門家への相談で将来を守る
外国人技能実習生による傷害事件のケースについて、刑事処分と強制送還のリスク、および取るべき対応策を解説しました。Aさんの事例からも明らかなように、日本人であれば罰金や執行猶予で済むようなケースでも、在留外国人にとっては本国送還という重大な結果につながりかねません。しかし、適切かつ迅速な対応によって刑事処分を軽減し、退去強制を回避できる可能性があります。
鍵となるのは、事件発生後できるだけ早く専門家である弁護士に相談することです。弁護士の力を借りて示談交渉や入管対応を進めれば、前科をつけずに済んだり、日本に引き続き在留できる道が開けるかもしれません。本人はもちろん、雇用主やご家族も一丸となってサポートし、専門家と協力して事態の打開を図りましょう。早めの相談・依頼が、外国人であるあなたの日本での未来を守る大きな一歩となるのです。
経営・管理ビザの外国人が速度違反で罰金!在留資格更新や退去強制への影響とは?
「経営、管理」の在留資格で日本に滞在しているAさんは、適法な運転免許証を所持し、自家用車を保有していました。
ある日、Aさんは、自動車で帰宅中、周りの景色に気を取られてしまったことが原因で、思ったより速度が出てしまいました。
たまたま速度違反の取り調べを受けていた警察官によって速度が計測されてしまい、違反の事実が明らかになってしまいました。
このとき
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰は、Aさんの在留期間の更新時に影響があるか、若しくは退去強制処分となるか
以上の点について解説していきたいと思います。
⑴速度違反の刑事罰
今回は速度違反についての問題です。
速度違反については、「反則金」(青切符)で処理される場合と、「罰金」(赤切符)で処理される場合の2種類があります。
どちらになるのかは、①どのような道路での違反か②何キロオーバーかの2つの点から決定されることになります。
一般道の場合、30キロオーバー以上が赤切符であり、それ未満は青切符です。
高速道路などの場合には、40キロオーバー以上が赤切符であり、それ未満は青切符です。
青切符の場合、いわゆる行政罰の一種として処理されることになりますので、前科にはなりません。
これに対して赤切符の場合には、「罰金」ですから、前科となります。
ですので、Aさんがどこで、何キロオーバーしたかで処分が異なるということになります。
⑵「経営、管理」の在留資格について
在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」(出入国管理及び難民認定法21条2項)に認められますが、この認定にあたっては、出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。
このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用。動労条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。
このうち4の部分には「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。
まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、入管法上別表第1の2の表に記載がある在留資格です。
そのため、法務省令に定める上陸許可基準等に適合する必要があります。
この上陸許可基準は公表されていますが、概ね業務に関する事項や報酬についての定めが記載されています。ですので、仮に過失運転致傷によって処罰されたからといって上陸許可基準に該当しないというものではありません。
今回の場合、ガイドラインに記載されている「素行が不良でないこと」が問題となります。そして、「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた」場合には素行不良であると判断されることになるため、退去強制事由に準ずるような刑事処分であるかどうかを検討していくことになります。
それでは刑罰法令違反が退去強制事由となるかどうかを考えていきます。別表第1の在留資格の場合、入管法等在留関係の法律以外の刑罰法令が問題となる退去強制事由には、入管法24条4号リと同法24条4号の2があります。
まず、入管法24条4号リは、「無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。」とするものです。この4号リで問題とされるのは、実刑となった者、つまり執行猶予付きの判決を受けた場合は除かれています。速度違反の罪で実刑の判決となるのは複数回検挙されるとか、想定し難い速度違反等に限られると思われますので、典型的な速度違反ではこれに該当しない可能性の方が高いと思われます。
次に、24条4号の2ですが、こちらは一定の犯罪で拘禁刑に処せられた場合に退去強制事由となるものです。24条4号リとの違いは、罪名の違いがあるものの、執行猶予付きの判決であっても退去強制事由となる点にあります。ただ、Aさんが問題視されている速度違反は、この列挙された犯罪に含まれていませんから、これには該当しません。
最後に、次に、Aさんの処分が退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで評価されることがあるかどうかが問題となります。
この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。
この審査要領は一般の在留期間の更新にも該当すると考えられます。そのため、Aさんについても同じように考えることになりますが、かっこ書きで除外されているのは「道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑」となっており、速度違反での赤切符はこれに該当します。
だからといってこの赤切符のことを秘して在留期間更新申請を行うことはできませんので、入管当局に正直に説明し、二度と運転しないこと等の誓約を行い在留許可の更新を求める方がよいと思われます。
在留資格を持っている状態で速度違反をしてしまった場合には、期間の更新のためいち早く弁護士にご相談ください。
永住者が偽造クレジットカード事件で逮捕された場合の刑事罰と強制送還の可能性
永住者が偽造クレジットカード事件に関与した場合の刑事罰と入管法上のリスク
永住権を持つ外国人が偽造クレジットカードの密輸に関与した場合、日本の法律でどのような刑事罰を受ける可能性があるのか、また入管法上のリスクとして退去強制(強制送還)があり得るのかについて解説します。具体的な事例として、永住者であるAさんが母国から帰国する際に偽造クレジットカードの原料(いわゆる「生カード」)を大量に持ち込もうとして逮捕されたケースを参考に説明します。
偽造クレジットカードを輸入した場合の刑事処分
まず、クレジットカードの原料となるプラスチック製の生カード(カード情報を書き込む前のブランクカード)は、日本の関税法で輸入が禁止されています。関税法第69条の11第1項6号は、偽造通貨や偽造有価証券と並んで、「不正に作られた支払用カード(預貯金の引出用のカード)を構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む)」を輸入禁止品に指定しています。
この規定に違反して禁止品を密輸入した場合、関税法第109条1項により10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金(またはその併科)という重い刑罰が科せられます。
量刑を左右するポイント
偽造クレジットカードの原料を密輸した場合の刑事処分の重さは、以下のような事情によって判断されます。
-
持ち込んだ枚数: 持ち込んだ生カードの枚数が多いほど犯行は重大と見做され、刑が重くなる傾向があります。
-
認識の程度: 密輸した物が偽造カード用だと知っていたか、その認識の深さも量刑に影響します。故意が明確であるほど不利になります。
-
完成品か否か: 偽造カードそのもの(カード情報が記録された完成品)を持ち込んだ場合と、情報を書き込む前の生カードを持ち込んだ場合とでは、後者の方がいくらか情状が考慮され得ます。
-
前科の有無: 過去に同種またはその他の犯罪歴がない初犯であれば、量刑上有利な事情となります。
今回のAさんの事例では、生カードを3,000枚と極めて多数持ち込もうとした点や、カード会社勤務の友人から「クレジットカードの原料」と聞かされて依頼を引き受けている点から、悪質性が高いと判断される可能性があります。一方で有利な事情としては、完成品の偽造カードそのものではなく原料の持込であったこと、そして前科がない初犯である点が挙げられます。
判例や傾向を見ると、1,000枚を超える規模で生カードを密輸した場合は執行猶予の付かない1年以上の実刑判決も視野に入ってきます。
数千枚規模の生カード密輸事件で実刑判決が言い渡された例もあり、今回のAさんも裁判では実刑かどうかが争われるか可能性が高いと言えるでしょう。
永住者に対する入管法上のリスク(退去強制処分)
次に、刑事罰を受けた場合の入管法上のリスクについてです。外国人の永住者であっても、一定の重大な犯罪で有罪判決を受けた場合には退去強制(日本からの強制送還)の対象となり得ます。入管法第24条第4号のリ(4号ニ~チに該当する場合を除く)では、「昭和26年11月1日以降に無期または1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」は退去強制事由に該当すると規定されています。今回のAさんのケースでは、上述のとおり1年以上の実刑判決が見込まれるため、この規定に該当し強制送還は避けがたい状況と言えます。
※ただし入管法の規定上、「1年を超える刑」が対象であり、刑がちょうど1年であった場合や刑の全部執行猶予が付いた場合などは直ちに退去強制とはなりません。
Aさんの場合、情状からして執行猶予なしの実刑となるか、執行猶予となるか、刑事裁判でも激しく争われることが予想されます。刑事裁判での判決内容が、入管法上のリスクと直結することになるため、刑事裁判の時点で適切な弁護活動を実践するのが好ましいでしょう。
弁護士による対応策と早期相談の重要性
このような事態に陥った場合、刑事弁護人として取れる対応策はいくつか考えられます。
-
無罪主張(故意の否定) – 持ち込んだ生カードが違法なものとは知らなかった等、犯意がなかったことを主張して無罪を争う方法です。しかし、本件では友人から「クレジットカードの原料」と説明を受けており違法性の認識を完全に否定するのは難しく、現実的には無罪を勝ち取るのは困難でしょう。
-
在留特別許可の申請 – 実刑判決が言い渡された場合でも、日本に生活基盤があり引き続き在留を希望するのであれば、法務大臣の裁量による在留特別許可の取得を目指すことになります。刑事裁判の段階から将来的な在留特別許可を見据えて情状を積み重ねるなどの弁護活動が必要であり、家族関係や更生の可能性を示して退去強制を免れるよう働きかけます。
いずれにせよ、家族や知人が偽造クレジットカードの密輸に関与して逮捕されてしまった場合、早急に刑事事件と入管手続双方に精通した弁護士に相談することを強くお勧めします。適切な弁護活動によって、刑事処分の減軽や在留継続の可能性を探ることができるからです。
具体的な事件についてお困りの方はこちらからお問い合わせください。
外国人が罪を犯したら退去強制に?|刑事事件と在留資格への影響・弁護士相談の重要性
外国人が罪を犯してしまったときに、すぐ弁護士へ相談すべき理由
日本に滞在する外国人が罪を犯してしまった場合、単に刑事罰を受けるだけではなく、在留資格の更新拒否や退去強制(強制送還)といった重大なリスクを抱えることになります。
こうしたリスクは日本人の場合よりも大きく、本人だけでなく家族や勤務先にまで深刻な影響を及ぼします。
だからこそ、トラブルが発生した時点で、できる限り早期に弁護士へ相談することが重要なのです。
外国人が刑事事件を起こしたときに直面するリスク
外国人が日本で刑事事件を起こした場合、日本人と同様に刑事罰を受けることになりますが、それに加えて在留資格への影響が避けられません。刑事事件の結果として有罪判決を受ければ前科が残り、入管当局の在留資格更新審査で「素行不良」と判断される可能性があります。特に、入管法24条に定められた退去強制事由に該当すれば、刑の内容にかかわらず強制送還の対象となります。退去強制の手続きは、入国警備官の調査、入国審査官の審査、口頭審理、法務大臣の裁決を経て進行し、最終的に日本からの退去を命じられることがあります。つまり、外国人が刑事事件を起こすことは、日本人以上に生活基盤を揺るがす重大なリスクを伴うのです。
事例
経営・管理ビザで日本に滞在していたAさんは、ある晩に友人と飲酒した後、自宅まで自転車で帰宅しようとしました。ところが、途中で警察官に呼び止められ、呼気検査を受けたところ基準値を超えるアルコールが検出され、自転車飲酒運転として検挙されてしまいました。自転車であっても飲酒運転が刑事罰の対象となることは、2024年の法改正により明確に定められています。Aさんは初犯で事故もなく、処分は罰金刑にとどまる可能性が高いですが、有罪判決を受けることで前科が付きます。外国人にとってこの前科は、将来の在留資格更新に大きな影響を与え、最悪の場合、退去強制につながるリスクを抱えることになるのです。
刑事罰と退去強制の関係
退去強制とは、日本から外国人を強制送還する手続きのことを指し、入管法24条に根拠があります。主な退去強制事由は、①薬物事件で有罪判決を受けた場合、②1年以上の懲役・禁錮刑を受けた場合、③一定の刑法犯(窃盗、詐欺、傷害など)で懲役刑に処せられた場合です。特に注意すべきは、執行猶予付きの判決であっても退去強制の対象になる点です。退去強制の手続きは、入国警備官による調査から始まり、入国審査官の審査、必要に応じて口頭審理や法務大臣の裁決を経て進みます。
違反認定をされてから実際に退去強制の命令が出されるまでの間に、日本での在留を希望する場合には在留特別許可申請をしなければなりません。たとえ軽微な違反であっても、刑事罰と退去強制の関係を正しく理解し、早期に備えることが重要です。
在留資格更新への影響
外国人が日本に在留し続けるには、在留資格の更新が必要です。この更新にあたっては「素行が善良であること」が要件とされています。有罪判決を受けると、この要件を満たさないと判断され、更新が不許可になる可能性があります。更新が認められないまま在留期限を迎えるとオーバーステイとなり、結果的に退去強制事由に該当してしまいます。特に経営・管理ビザのように事業活動を伴う資格では、社会的信用の低下がビザの継続に直結します。刑事事件自体が直ちに退去強制に当たらなくても、将来的な更新不許可という形で影響が現れるのが外国人特有のリスクです。したがって、軽微な罰金刑であっても安易に考えず、在留資格への影響を意識して行動する必要があります。
早期相談のメリット
刑事事件で検挙された段階で、できる限り早期に弁護士へ相談することには大きなメリットがあります。まず、刑事手続きでの適切な弁護活動により、罰金刑にとどめたり、不起訴処分を獲得したりできる可能性があります。処分が軽減されれば、在留資格への悪影響も最小限で済みます。また、入管手続きへの備えとして、在留特別許可の申請や善良な素行を示す資料の準備を前もって行うことができます。さらに、退去強制手続きは迅速に進むため、弁護士の助言なしでは手遅れとなる危険があります。早期に相談することで、刑事弁護と入管対応を並行して進められる点は大きな利点です。処分確定後では選択肢が限られるため、「まだ処分が出る前」に弁護士に依頼することが将来を守る最大の鍵となるのです。
外国人事件に詳しい弁護士の重要性
外国人が刑事事件を起こした場合、対応する弁護士が外国人事件に精通しているかどうかが結果を大きく左右します。刑事弁護の知識だけではなく、入管法や退去強制手続、在留特別許可の実務に精通していなければ、十分なサポートは困難です。例えば、日本人なら罰金刑で済む場合でも、外国人の場合は在留資格の更新不許可につながりかねません。こうした影響を見据えた弁護活動ができるかどうかが、専門性のある弁護士かどうかの分かれ目です。さらに、入管局に提出する書類の準備や、家族・事業の事情を説明する戦略立案なども、外国人事件に強い弁護士なら適切にサポートできます。刑事事件と入管手続きの双方を理解した弁護士に依頼することが、外国人本人と家族の生活を守るための不可欠な条件といえるでしょう。
事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と入管事件の双方に精通した弁護士が在籍し、外国人の方々が直面する複雑な問題に総合的に対応しています。これまで多数の外国人事件を取り扱い、刑事弁護活動と退去強制手続、在留特別許可申請に関する豊富な実績を有しています。逮捕直後から接見に対応し、証拠収集や反省文の作成支援などを迅速に行う体制を整えています。また、在留資格の更新に不安がある段階でも、専門的視点からアドバイスを行い、必要な準備をサポートします。当事務所では、ご本人やご家族に寄り添い、最善の解決策を提案いたします。外国人事件でお困りの際は、どうぞ早期にご相談ください。
お問合せはこちらから。
外国人永住者が不法就労助長罪に疑われたらどうなる!?
外国人の人材派遣業に関するリスクはこちらでも解説しています。
フルサイズの解説はこちらから。
日本で永住資格を持つ外国人が刑事事件に関与してしまうと、刑事罰だけでなく在留資格(永住資格)やこれまで築いてきた生活基盤を失う危険があります。
特に「不法就労助長罪」の疑いをかけられた場合、そのリスクは極めて深刻です。
この記事では、不法就労助長罪とは何か、その成立要件や法定刑、疑われた場合に受ける刑事上のリスクと永住資格への影響について、入管・刑事事件に精通した法律事務所の視点から解説します。
また、取調べへの対応方法や弁護活動のポイント、早期に弁護士へ相談する重要性についても紹介いたします。
不法就労助長罪とは
「不法就労助長罪」とは、外国人に不法就労(在留資格外の違法な就労)をさせたり、その行為を助けたりする行為を処罰する犯罪です(不法就労をした外国人本人を罰する「不法就労罪」とは別個の犯罪です。)
なお、日本人であっても処罰の対象になります。
典型的な例としては、事業主が在留資格を持たない外国人を自分の店で働かせるケースや、業者が不法就労させるために外国人を集めて紹介するブローカー行為を行ったケースなどが挙げられます。
この罪の法定刑は3年以下の拘禁または300万円以下の罰金(またはその併科)と非常に重く、また個人とは別に法人(会社)にも罰金刑が科されます。また、不法就労助長罪は令和6年の法改正により厳罰化することが決定しており、改正法が施行されると法定刑が「5年以下の拘禁または500万円以下の罰金(またはその併科)」に引き上げられる予定です。
そして、外国人自身がこの罪を犯した場合は入管法上の退去強制(強制送還)の対象ともなります。
事例(永住者が不法就労助長罪で疑われたケースを想定)
Aさんは永住権を持って日本に在留している外国人で、国内で飲食店を経営しています。
ある日、Aさんは外国人留学生のBさんを在留資格や在留期限を確認せずに「アルバイトスタッフ」として採用し、違法になるとは知らず店で働かせはじめました。
ところが後日、警察の摘発によりBさんが不法残留(オーバーステイ)の疑いで逮捕されてしまいました。
その事件の捜査の過程で、実はBさんの在留資格が「留学」であり、Aさんが採用した時点ですでに在留期限を超えていたことが明らかになりました。
その結果、Aさんも「外国人に不法就労をさせた」容疑で警察に逮捕される事態となってしまいました。
自分は悪意なく雇っただけと思っていたAさんにとって、まさに青天の霹靂と言える状況です。
刑事罰のリスクと影響
不法就労助長罪が成立した場合、現行法の法定刑は「3年以下の拘禁」または「300万円以下の罰金」、もしくはその両方と定められています(法改正後の厳罰化については既にお話した通りです)。
具体的な刑の重さを決める際には、不法就労させた外国人の人数や就労させた期間といった事情が考慮され、その人数が多いほど、期間が長いほど処罰が重くなる傾向があります。
初犯であれば執行猶予付きの拘禁刑に加えて罰金刑が一緒に科されるケースが多いようです。
特に注意を要する点として、入管法には、在留資格を確認せず外国人を働かせた場合には「知らなかった」「うっかり」では済まされず処罰されるという規定があります。
確認義務を怠った以上、雇った外国人の在留資格について問題ないと認識していたとしても、罪に問われてしまう可能性があるので注意が必要です。
もし逮捕・起訴されて有罪判決を受ければ前科がつき、社会生活や就労にも大きな支障をきたします。
更に、刑事裁判で実刑判決を受け服役する事態になれば、仕事や家庭など生活基盤への大きな打撃は避けられません。
特に、日本に在留している外国人にとっては、このまま日本に在留し続けられるかという重大な問題も生じてきます。これは、永住資格を有している人でも同じです。
永住資格への影響
永住者にとって重大なのは、有罪か否かにかかわらず不法就労助長の事実によって在留資格自体が危うくなることです。
不法就労助長を行った外国人は、入管法24条3号の4に定める退去強制事由に該当し、永住者であっても強制送還の対象となり得ます。
たとえ刑事事件については不起訴となるなど罰を受けなかった場合でも、在留資格の審査は裁判所とは別の機関である入管当局が取り扱うので、入管当局に不法就労助長行為が認められてしまうと、直ちに強制退去の手続きが進められてしまうおそれがあります。
そして、一度でも退去強制となれば永住許可は取り消され、日本からの出国を余儀なくされます。
日本での職場や家庭、暮らしの基盤を一瞬にして失ってしまう可能性があり、その影響は計り知れません。
永住資格を持つ方にとって、「本罪の嫌疑をかけられること」それ自体が、日本に住み続ける権利を失う非常に深刻なリスクを伴うのです。
取調べ対応と弁護活動
捜査段階で警察から取調べを受ける際には、自身の権利を理解し慎重に対応する必要があります。
取調べを受ける人には黙秘権(話したくないことは話さなくてよい権利)が保障されており、警察に言われるがままに供述する義務は全くありません。
不用意な発言が自分に不利な証拠となりかねないため、可能であれば弁護士と相談した上で取調べに臨むことが望ましいでしょう。
弁護士から取調べ対応のアドバイスを受ければ、供述内容に注意しながら適切に対処でき、結果的により重い刑罰を避けることにもつながります。
また、弁護人となった弁護士は、早い段階で検察官と交渉し、有利な事情を示して不起訴処分や減刑を求める弁護活動を行います。
さらに、永住者の場合は悪質な故意がなく過失にとどまることなどを、入管当局に対しても事案に応じて強調し、退去強制処分を避けるよう弁護します。
このように専門家による適切な弁護活動によって、刑事処分や強制送還といった最悪の事態を回避できる可能性があります。
早期の弁護士相談の重要性
不法就労助長罪の疑いをかけられた場合、できるだけ早く弁護士に相談することが肝心です。
刑事事件は時間との勝負であり、初動の対応次第でその後の結果が大きく変わります。
特に逮捕後は警察での取調べと並行して在留資格取消しの調査が進むケースもあります。
しかし、国選弁護士(裁判所が選任する弁護人)は刑事事件のみを担当する弁護士であり、入管当局によるビザ取消し手続きには関与できないため、永住資格を守るためにはビザにも対応できる私選の弁護士を早急に依頼する必要があります。
早期に経験豊富な弁護士に相談すれば、刑事弁護と入管手続の両面にわたる戦略を立てることが可能です。
例えば、証拠が揃う前に適切な弁解を準備したり、必要に応じて入管当局への働きかけ(在留特別許可の申請等)を検討したりと、打てる手は格段に増えます。
事態が深刻化する前に専門家のサポートを受けることで、処分の軽減や在留資格維持の可能性を高められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本でも数少ない刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国規模の法律事務所です。
全国の主要都市に拠点を構え、外国人の入管在留案件を含む様々な刑事事件で豊富な実績を有しています。
特に、入管手続にも精通した弁護士および行政書士チームが在籍しており、刑事手続と在留資格手続の両面でワンストップの法的サポートが可能です。
永住者を含む在日外国人の権利と生活を守るために全力で対応いたします。
当事務所では24時間365日、初回無料法律相談を受け付けております。
永住者の方で刑事事件について不安がある方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
永住外国人がフェンタニルで逮捕されたら?―刑事罰と退去強制リスク、早期の弁護士相談が重要
事例紹介:永住者Aさんのフェンタニル使用事件
永住資格を持つ外国人のAさんは、母国からごく少量のフェンタニルを日本に持ち込み、国内で自己使用しました。しかし病院に搬送され、診察で麻薬使用の疑いが浮上しました。尿検査などの結果、Aさんがフェンタニルを使用していたことが判明し、その場で逮捕されてしまいました。Aさんには前科がなく、今回が初めての違法行為でした。このケースを通じて、逮捕・起訴から在留資格への影響までを見ながら、「早期に弁護士へ相談する重要性」を考えていきます。
フェンタニル使用の刑事罰:初犯でも油断できない
フェンタニルとは医療用鎮痛剤として使われる成分ですが、乱用すると幻覚症状を引き起こし、過剰摂取により死亡事故も起きている非常に危険な薬物です。そのため日本では「麻薬及び向精神薬取締法」(麻向法)により輸入・所持・使用が厳しく禁止されています。フェンタニルは同法の規制対象(別表第一77号が指定する麻薬)に指定されており、正当な医療目的以外で使用しただけでも犯罪となります。
この麻向法66条の2第1項では、麻薬(フェンタニル等)の使用罪の法定刑は「7年以下の拘禁刑」と定められています。つまりAさんの場合、たとえ少量の使用でも最悪7年の拘禁刑(懲役刑)を科される可能性が法律上はあるわけです。ただし実際の量刑は個々の事情で異なり、一般に初犯で自己使用目的のみであれば比較的軽い傾向があります。過去の判例や傾向からすると、前科のない初犯の薬物使用者には執行猶予付きの判決が下されるケースもあります。Aさんも使用量がごく少量・使用回数も1回のみ・前科なしという状況から、執行猶予付きの懲役刑(いわゆる執行猶予判決)になる可能性が高いと予想されます。
しかし油断は禁物です。量刑は以下のような要素で重くも軽くもなります:
- 薬物の量: 持ち込んだ・使用した量が多いほど刑は重くなります。少量とはいえ油断できません。
- 使用(犯行)の回数: 常習性が疑われると厳罰化しやすく、回数が増えるほど悪質と見られます。
- 前科の有無: 前科があると再犯とみなされ刑が重くなります。初犯は情状酌量の余地があります。
Aさんは幸い初犯でしたが、もし営利目的(売買目的)で麻薬を扱っていた場合、初犯でも実刑(執行猶予なしの懲役刑)となる可能性が高くなります。このようにケースによって結果が大きく変わるため、刑事手続きの早い段階から専門家である弁護士と十分に打ち合わせをして対応策を練ることが極めて重要です。
逮捕から起訴まで:外国人だからこそのリスク
逮捕された後、警察による取り調べや身柄の拘束(勾留)が行われます。薬物事案では証拠隠滅や逃亡の恐れから逮捕・勾留が長引く傾向があり、場合によっては共犯者捜査のために接見禁止(家族などとの面会禁止)が付くこともあります。接見禁止が付されると弁護士だけが面会可能となるため、家族であっても本人と直接会えません。このような状況下でも弁護士であれば接見して本人の状況を確認し助言できます。早めに弁護士に依頼しておけば、孤立しがちな被疑者(本人)を励ますこともできます。
検察官が起訴(正式な裁判にかけること)するかどうかの判断は、事実関係を認めているか否か,証拠の強さによって決まります。Aさんの場合、尿検査で陽性反応が出ている以上起訴され公判にかけられる可能性が高いでしょう。
また,起訴後は保釈が認められない限り裁判が終わるまで勾留が続きます。保釈を勝ち取るには裁判所への請求と保証金の納付が必要で、法律の専門知識が要求されます。ここでも弁護士のサポートが不可欠です。早期に弁護士に相談していれば、勾留に対する不服申立てや保釈請求など迅速な対応が可能となり、場合によっては本人を早く解放させて通常の生活に近い状態で裁判に臨ませることも期待できます。
有罪判決で待ち受ける在留資格への影響:強制送還のリスク
Aさんのような外国人が日本で罪を犯し有罪判決を受けると、刑事罰だけでなく在留資格への重大な影響があります。日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)24条4号チという規定では、麻薬及び向精神薬取締法などの薬物に関する法律に違反して有罪判決を受けた外国人は退去強制(強制送還)の対象になると定められています。これは執行猶予付き判決であっても例外ではありません。執行猶予が付いて刑務所に行かずに済むとしても、「有罪判決を受けた」という事実に変わりはないため、入管法上は退去強制事由(国外退去させる理由)に該当してしまうのです。
その結果、原則として日本からの強制退去が待ち受けます。永住者であっても、この退去強制を回避しない限り日本に住み続けることはできません。Aさんも仮に執行猶予判決となった場合でも、この規定に該当するため強制送還のリスクが生じます。
在留特別許可という最後の望み
とはいえ、一度の過ちで即座に生活基盤を奪われてしまうのは本人・家族にとって大変深刻です。そこで法律上、退去強制の対象になった外国人にもわずかながら救済の途があります。それが「在留特別許可」と呼ばれる制度です(出入国在留管理局HP)。退去強制となる事情があっても、法務大臣の裁量で特別に日本への在留を許可してもらえる可能性があります。例えば日本人の配偶者や子どもがいる場合、長年日本で暮らして地域に溶け込んでいる場合などは、積極的に考慮される「在留すべき事情」となり得ます。
Aさんの場合、永住者ということは日本に生活の本拠があり、家族や仕事など日本での生活基盤があると考えられます。それらを根拠に「日本に引き続き在留する必要性(情状)」を主張できれば、在留特別許可が与えられる余地があります。ただし在留特別許可は自動的にもらえるものではなく、あくまで「特別に許可」されるものです。申請や審理の過程で日本に残るべき正当な理由を具体的に示し、入管当局に認めてもらわなければなりません。
弁護士ができること:刑事弁護から在留特別許可のサポートまで
弁護人(弁護士)としてAさんのようなケースでできることは大きく分けて2つあります。一つは刑事手続における弁護活動、もう一つは在留資格に関わる手続(在留特別許可)の支援です。
- 刑事弁護活動: まず刑事裁判においてできる限り情状酌量を引き出し、量刑を軽減するよう努めます。具体的には、犯行に至った経緯や本人の反省状況、今後再犯しないための環境(治療計画や家族の監督体制など)を丁寧に主張し、執行猶予付き判決や減刑を目指します。初犯であることや使用量の少なさなど有利な事情は最大限強調し、裁判官に「更生可能性が高い」と判断してもらうことが重要です。また、勾留中であれば早期の保釈請求も行い、社会復帰しやすい環境で裁判を受けられるよう手配します。
- 在留特別許可のためのサポート: 有罪判決によって退去強制手続きに移行した場合、在留特別許可の申請手続きを全力でサポートします。具体的には、本人および家族の状況を詳しくヒアリングし、日本に残る必要性を示す資料(家族関係を証明する書類、嘆願書、雇用証明、納税記録など)を収集・提出します。
なぜ早期相談が重要なのか:逮捕後すぐ動くことのメリット
以上のように、外国人が罪を犯した場合には「刑事罰」と「在留資格の剥奪」という二重のリスクに直面します。しかし逆にいえば、早めに専門の弁護士に相談することで刑事手続と入管手続の両面に備えることが可能となります。逮捕直後から弁護士が付けば、取り調べ段階での助言や権利擁護(黙秘権の行使や供述調書のチェックなど)を受けられ、不利な証言を避けられるかもしれません。また、家族との連絡調整や必要書類の収集も早期から開始できます。裁判で有利な証拠や嘆願書の準備、さらには在留特別許可のための資料作成も、時間的猶予をもって進められます。
一方、対応が遅れると手遅れになるリスクがあります。例えば有罪判決が確定してから慌てて在留特別許可の準備を始めても、充分な主張を組み立てる時間がないかもしれません。場合によっては拘束中に強制送還の日程が進んでしまい、準備が整わないまま本国送還となりかねません。早期に信頼できる弁護士に相談し、刑事弁護と入管対応を一貫して依頼しておけば、そのような最悪の事態を避けられる可能性が高まります。
おわりに:家族のためにも迅速な相談を
永住外国人やそのご家族にとって、日本で築いた生活基盤を犯罪によって失うことは想像を絶する不安でしょう。しかし、逮捕・起訴されたとしても諦めず、まずは弁護士に相談することが肝心です。専門の弁護士であれば、刑事裁判での戦略立案から在留特別許可の申請まで総合的にサポートしてくれます。Aさんのケースでも述べたように、初犯なら執行猶予の可能性があり刑務所行きを避けられるかもしれません。さらに判決後も適切に対応すれば、在留特別許可を得て日本に住み続ける道が開ける可能性もあります。そのためには時間との勝負です。問題が発覚した時点で一刻も早く弁護士に相談し、今後の見通しや取るべき手段についてアドバイスを受けてください。逮捕・起訴・強制送還という最悪の結果を防ぎ、かけがえのない生活と家族を守るために、早期の弁護士相談が何より重要なのです。
定住者が盗難車を買ったらどうなる?盗品有償譲受罪の刑事処分と退去強制の可能性
【事例】
Aさんは、日本に定住者の資格で在留する外国人です。Aさんは、中古車販売を行う会社を経営しています。
ある日、友人から紹介された中古車の販売をするBさんから、この車を売りたいと言われたことから、中古車を購入することになりました。
しかし、その自動車はなぜか、鍵穴が壊され、ナンバープレートが取り外されており、この車を持っていたとされるCさんからBさんに所有者が移ったのか車両番号から明らかでありませんでした。そのため、AさんはBさんに「盗難車じゃないのか」と聞いたところ、「そうじゃない」と言われました。そのため、盗難車でないなら買い取ろうと思って100万円で購入しました。
なお、Aさんはこれまで、盗品の中古車を会社で買うことはありませんでした。また、Aさんには前科等はありませんでした。
そうやってBさんから中古車を購入して数か月たったころ、警察から、盗品有償譲受の疑いで会社に対する捜査が入り、Aさんは逮捕されてしまいました。
このような場合に、①どのような刑事処分を受けるのか、②退去強制処分になるのかについて解説していきます。
(1)盗品有償譲受罪に対する刑事処分
刑法256条2項によれば、「前項に規定する物(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物)を…(中略)…有償で譲り受け」た場合に盗品有償譲受罪が成立し、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金の刑に処されるとされます。注意が必要なのは、盗品関与罪に当たる罪を犯した場合、必ず、懲役刑(執行猶予も含む)と罰金が科されるということです。
盗品有償譲受罪が成立した場合の量刑傾向は、①被害品の価格、②業務として継続的にやっているか否か、③前科があるかなどによって判断されます。
①については、金額が大きければ大きいほど重く見られます。
②については、継続的にやっていれば、やっているほど重く見られます。
③については、前科があれば、重く見られます。
今回のAさんの場合、金額が100万円と高額ですが、これまで盗品の中古車を買い受けていないこと、前科がないことが有利な事情として考慮されて、執行猶予付きの有罪判決に罰金刑が併科される可能性が高いです。
(2)退去強制処分の可能性について
定住者が退去強制処分になるかどうかについては、入管法24条4号リに規定があります。
これによれば、1年以上の実刑判決を受けた場合には、退去強制処分の対象となります。
本件事案におけるAさんは、執行猶予付きの有罪判決と罰金の刑罰を受けることが予想されることから、退去強制処分になるとは考えにくいです。
(3)弁護士にできること
弁護士としてできることとしては、①中古車が盗品だと知らなかったと主張して無罪判決を得ることのできるよう活動すること、②被害者と示談して、不起訴を目指す活動をすることが考えられます。
①のように、中古車が盗品だと知らなかったと主張するためには弁護士を付けて対応することが望ましいこと、②示談をして、不起訴を目指すためには、弁護士を付けることが望ましいことから、盗難車の売買に関わって、お困りの方は迅速に弁護士に相談されることをお勧めします。
« Older Entries